こんにちは!今回は、日本統治下の朝鮮半島で林業技手として山々の緑化に尽力しながら、誰よりも朝鮮の文化と人々を愛し抜いた浅川巧について解説します。
彼は公的な立場にありながら朝鮮服を纏い、現地の言葉を話し、キムチを食べてオンドルで眠り、朝鮮の工芸品「膳」や「陶磁器」の美しさを世界で初めて体系的に見出しました。
「朝鮮の土になった日本人」とも呼ばれる彼の、国境と時代を越えた40年の生涯を紐解いていきましょう。
浅川巧の原点となった故郷山梨とキリスト教の精神

若き浅川巧が農林学校で育んだ自然への眼差し
明治24年、山梨県北巨摩郡甲村に生まれた浅川巧は、豊かな自然に囲まれて少年時代を過ごしました。彼の生家は醸造業などを営む家系でしたが、巧が生まれてすぐに父を、10歳で祖父を相次いで亡くしています。一家の柱を失い、決して裕福とは言えない環境でしたが、母の気丈な働きと兄たちの存在が彼を支えました。また、故郷の山々や草花に対する深い愛情は、幼少期から青年期にかけて確実に育まれていきました。
地元の農林学校に進学した巧は、そこで近代的な林業技術の基礎を学びます。当時の農林教育は、単に木材を生産するための技術習得にとどまらず、自然界のサイクルや土壌の性質、そして植物がいかにして環境と調和して生きているかを観察する科学的な視点を彼に授けました。山梨県は山がちな地形であり、治水や治山が生活に直結する土地柄でもあります。巧は、荒れた山がいかに人々の生活を脅かすか、逆に豊かな森がいかに人々の心を潤すかを、身をもって感じていたことでしょう。
彼が農林学校で学んだことは、後の朝鮮半島での活動に直結します。植物を単なる資源としてではなく生命として捉える眼差し、そしてその土地ごとの風土に逆らわずに育てるという姿勢は、この頃に培われたものです。教科書的な知識だけでなく、実際に山に入り、土に触れる中で得た感覚こそが、彼が生涯大切にし続けた自然への謙虚さの源流となったのです。この時期に培われた観察眼は、後に朝鮮の陶磁器や木工品を見る際にも、その素材や作られた背景を見抜く確かな目として機能することになります。
小宮山清三らと語り合った白樺派や人道主義の影響
青年時代の浅川巧を語る上で欠かせないのが、同郷の友人である小宮山清三らとの交流と、キリスト教および「白樺派」の影響です。巧は農林学校在学中の16歳の時にキリスト教の洗礼を受けており、その精神的土壌は早くから形成されていました。彼が信仰したのは、形式的な教義に縛られた宗教ではなく、イエス・キリストの生き方に倣い、隣人を自分のように愛するという実践的な信仰でした。
農林学校を卒業後、営林署に勤務しながらも、巧は文学や芸術に関する書物を貪るように読みました。特に志賀直哉や武者小路実篤らが提唱した白樺派の人道主義は、巧のキリスト教精神と深く共鳴しました。小宮山清三ら親しい友人たちとは、夜遅くまで人生や芸術、信仰について熱く語り合ったといいます。彼らの議論は観念的なものにとどまらず、いかに生きるべきかという切実な問いに基づいたものでした。
彫刻家を志し、オーギュスト・ロダンに憧れていた兄・浅川伯教の影響もあり、巧もまた芸術や真理に対する鋭い感性を持っていました。林業家としての実直さと、芸術家のような魂を併せ持つ巧。キリスト教の精神と白樺派のヒューマニズムは、彼の中で「すべての人間は平等であり、民族や立場の違いを超えて理解し合えるはずだ」という揺るぎない信念へと昇華されていきます。この精神的土壌があったからこそ、彼は後に植民地という歪んだ構造の中でも、決して人間としての尊厳を見失わずに生きることができたのです。
安定を捨てて兄のいる朝鮮へ向かった浅川巧の決断
大正3年、23歳になった浅川巧は大きな決断を下します。それは、秋田県の大館営林署での安定した仕事を辞し、兄である浅川伯教が暮らす朝鮮半島へ渡ることでした。兄の伯教はすでに朝鮮に渡り、小学校の教師をしながら現地の陶磁器の魅力に取り憑かれていました。兄からの手紙には、朝鮮の美しさとともに、荒廃した山々の惨状も綴られていたのかもしれません。あるいは、巧自身の中に、新しい天地で自分の力を試してみたいという冒険心があったのでしょうか。
周囲の人々にとって、この決断は驚きでした。当時の朝鮮は日本の統治下にありましたが、生活環境や治安の面で不安視する声も少なくなかったからです。しかし、巧の意志は固く、彼は迷うことなく海を渡りました。この決断の背景には、敬愛する兄への信頼と、自らの林業技術をより困難な場所で役立てたいという使命感があったと考えられます。また、日本国内でのキャリアや閉塞感から離れ、より広い世界で人間としての生を全うしたいという渇望もあったのかもしれません。
彼が朝鮮行きを決めた瞬間、それは単なる引っ越しではなく、彼の運命を決定づける旅立ちとなりました。故郷の山々で培った技術と、読書と対話によって育まれた精神性、そして兄への思慕。これらすべてを携えて、浅川巧は釜山の土を踏みます。そこには、彼の想像をはるかに超える厳しい現実と、魂を揺さぶる美しい出会いが待っていました。この渡航こそが、後の朝鮮の土となった日本人誕生の第一歩だったのです。
浅川巧を朝鮮へ導いた兄伯教と運命的な白磁との出会い

技手として京城に降り立った浅川巧が見た禿山の現実
朝鮮半島の中心都市、京城(現在のソウル)に到着した浅川巧の目に飛び込んできたのは、故郷山梨の緑豊かな山々とは対照的な、赤茶けた「禿山(はげやま)」の姿でした。長い歴史の中での過度な伐採や、オンドルの燃料としての落葉採取、そして厳しい気候条件が重なり、当時の朝鮮の山々は見るも無惨に荒廃していました。雨が降れば土砂が流出し、洪水を引き起こす原因ともなっていたのです。
朝鮮総督府農林局林業試験場の技手として採用された巧にとって、この光景は衝撃であり、同時に自らが取り組むべき巨大な課題として立ちはだかりました。日本の豊かな森林での常識は、ここでは通用しません。土壌は痩せ、乾燥しており、苗木を植えてもなかなか根付かない過酷な環境でした。しかし、巧はこの現実に絶望するのではなく、むしろ林業家としての闘志を燃やしました。「この山々を再び緑に戻すことができれば、朝鮮の人々の暮らしは豊かになるはずだ」。そう信じた彼は、試験場の同僚たちと共に、泥にまみれる日々をスタートさせます。
彼の仕事は、単に机の上で計画を立てることではありませんでした。自ら鍬を持ち、試験場の苗畑を耕し、朝鮮の気候に適した樹種を探し求める地道な研究の日々でした。荒涼とした風景の中に立ち尽くしたとき、彼の心には「支配者としての日本人」ではなく、「傷ついた大地を癒やす医師」のような使命感が芽生えていたのかもしれません。この禿山との対峙が、彼の朝鮮での活動の基盤となり、やがてそれは大地への愛着へと変わっていきます。
柳宗悦という盟友との邂逅と「膳」に見出した美
大正5年、浅川巧の運命を大きく変える人物が京城を訪れます。白樺派の中心人物であり、宗教哲学者、そして後に民芸運動を興すことになる柳宗悦です。実は二人はその前年、巧が休暇で帰国した際に千葉県我孫子の柳邸を訪ねており、すでに面識を得ていました。しかし、この京城での再会こそが、二人の魂を深く結びつける決定的な瞬間となりました。柳は、巧の兄・伯教から贈られた「染付秋草文面取壺」に魅了され、その美の源泉を確かめるために朝鮮へとやってきたのでした。
柳はこの旅で巧の家に滞在し、二人は寝食を共にしながら芸術や人生について語り明かしました。柳宗悦の鋭い審美眼は、巧にも大きな影響を与えました。しかし、巧自身もまた、柳にはない独自の視点を持っていました。それは、日常の暮らしの中で使われる道具への温かい眼差しです。ある日、巧は市場で売られている粗末な「膳(ソバン)」に目を留めます。それは、朝鮮の人々が食事の際に使う小さな足つきのお盆であり、ごくありふれた生活用具でした。しかし巧は、その使い込まれた木肌や、無駄のない機能的なフォルムに、飾らない美しさを見出したのです。
「これは美しい」と直感した巧は、膳を買い集め始めます。柳が主に陶磁器の美に注目したのに対し、巧は木工品や民具といった、より庶民の生活に密着したものに心を寄せました。膳の脚の曲線(猫足や狗足など)には、地方ごとの特色や職人の遊び心が表れています。巧はそれらを分類し、研究することで、名もなき職人たちが込めた手仕事の温かさを再発見していきました。この「膳」への開眼は、後に彼が提唱する「生活の中の美」という概念の核となっていきます。
浅川巧が心奪われた朝鮮陶磁の寂しくも温かい世界
兄・伯教の影響もあり、巧もまた朝鮮陶磁、特に「白磁」の虜になっていきました。李朝時代の白磁は、中国の磁器のような完璧な左右対称や華やかな装飾とは異なり、どこか歪んでいたり、肌に黒い斑点があったりと、不完全な部分があります。しかし、その乳白色の肌合いや、ぽってりとした温かみのある造形には、見る者の心を静める不思議な力がありました。柳宗悦はそれを「悲哀の美」と表現しましたが、巧はそこに「自然への順応」と「飾らない心」を見ていたようです。
巧は休日になると、兄や柳とともに骨董街や地方の窯跡を巡り歩きました。彼らは高価な美術品としてではなく、かつて人々の暮らしの中で使われていた器として陶磁器を愛でました。割れた陶片の一つひとつを拾い上げ、その断面や釉薬の流れを観察する巧の姿は、まるで植物の生態を調べる研究者のようでもありました。彼は、陶磁器が生まれる背景には、その土地の土や水、そして職人たちの精神性が深く関わっていることを直感的に理解していたのです。
特に巧が愛したのは、真っ白な白磁の中に、青い顔料で素朴な絵が描かれた「染付」でした。そこに描かれた草花や動物たちは、巧が愛した朝鮮の自然そのものでした。彼は陶磁器を通じて、朝鮮の人々の心の中に流れる美意識と対話していたとも言えるでしょう。この陶磁器への深い愛情は、後の『朝鮮陶磁名考』という不朽の名著へと結実していきますが、その原点は、京城の古道具屋で埃にまみれた器を手に取り、静かに微笑んだ若き日の感動にあったのです。
朝鮮服を纏い現地語で暮らした浅川巧の日々と友情

パジ・チョゴリで生活しオンドルで眠った浅川巧の真意
浅川巧を語る上で最も象徴的なのは、その生活スタイルです。彼は勤務中こそ制服を着ていましたが、家に帰るとすぐに朝鮮の伝統的な衣服である「パジ・チョゴリ」に着替えました。そして、食事にはキムチや朝鮮料理を好み、床暖房である「オンドル」の部屋で起居しました。当時の日本人の多くが、日本人居留地で日本式の生活を固守していたのとは対照的です。これは単なる趣味や異国情緒への憧れではなく、彼なりの明確な意思表示であり、合理的な選択でもありました。
巧は、「朝鮮で暮らすのだから、朝鮮の服を着て、朝鮮のものを食べ、朝鮮の家に住むのが一番理にかなっている」と考えていました。朝鮮の厳しい冬には、綿の入ったパジ・チョゴリとオンドルが最も暖かく快適であることを、彼は体感として知っていたのです。また、そこには「相手の文化を尊重し、同じ目線で生きたい」という深い敬意も込められていました。白い服を着て街を歩けば、朝鮮の人々は彼を日本人だと気づかず、自然に話しかけてきます。巧にとって、その垣根のない交流こそが何よりの喜びでした。
さらに彼は、朝鮮語の習得にも熱心でした。単なる片言ではなく、微妙なニュアンスや感情を伝え合えるレベルまで熟達していたといいます。市場での買い物では、現地の女性たちと冗談を交わしながら値段交渉をする姿が見られました。「日本から来たお役人」ではなく、「近所に住むちょっと変わった、でも人の良いおじさん」として、彼は市井の人々に受け入れられていったのです。この徹底した「生活者としての同化」が、彼の言葉や行動に真実味を与え、多くの朝鮮の人々の心を解きほぐしていきました。
南宮璧や廉想渉ら朝鮮の知識人と結んだ対等な絆
浅川巧の周囲には、常に朝鮮の芸術家や知識人たちがいました。中でも、詩人の南宮璧(ナムグン・ビョク)との友情は特別なものでした。彼らは林業試験場の同僚として出会い、共に植物を愛し、文学を語り合いました。植民地という支配・被支配の関係を超え、二人は「人間対人間」として魂をぶつけ合いました。巧は南宮璧の才能を高く評価し、彼の詩作を励まし続けました。南宮璧もまた、巧の誠実な人柄と朝鮮文化への深い理解に信頼を寄せ、心の友として接しました。
また、作家の廉想渉(ヨム・サンソプ)とも交流がありました。当時、朝鮮の知識人たちは日本の支配に対して複雑な感情を抱いていましたが、巧に対しては別格の親しみを抱いていました。巧の家は、日本人と朝鮮人が分け隔てなく集まり、夜遅くまで芸術論や将来の夢を語り合うサロンのような場所になっていました。そこでは日本語と朝鮮語が入り混じり、笑い声が絶えなかったといいます。
こうした交流の中で、巧は朝鮮の人々が抱える苦悩や悲しみ、そして誇りを肌で感じ取っていきました。彼は、友人が不当な扱いや差別を受けたときには、自分のことのように怒り、悲しみました。ある時、友人が警察に理不尽な尋問を受けた際、巧が身を挺して抗議したという逸話も残っています。真偽のほどは定かではありませんが、そうしたエピソードが語り継がれること自体、彼がいかに友人たちから信頼され、「我々の味方」と思われていたかを物語っています。彼の友情は、同情や憐れみではなく、相手を対等な人格として尊重する真の友愛でした。
職場の石戸谷勉や高木五六が信頼を寄せた仕事ぶり
浅川巧は、理想家であると同時に、極めて優秀な実務家でもありました。林業試験場での彼の上司であった石戸谷勉や、場長の高木五六は、巧の仕事ぶりを高く評価していました。石戸谷は植物分類学者であり、巧と共に朝鮮全土の植物調査を行いました。巧の観察眼の鋭さと、どんな過酷なフィールドワークも厭わない粘り強さに、石戸谷は全幅の信頼を置いていました。二人は学問的なパートナーとして、朝鮮の植生に関する膨大なデータを蓄積していきました。
場長の高木五六もまた、巧のよき理解者でした。高木は、巧が業務時間外に朝鮮語を勉強したり、工芸の研究に没頭したりすることを咎めるどころか、むしろ推奨し、温かく見守りました。高木自身も広い視野を持った人物であり、巧のような存在が、林業試験場にとって、ひいては日朝の架け橋として不可欠であることを理解していたのでしょう。巧が職場で見せる誠実さは、日本人職員の間でも一目置かれていました。
巧は、自分の給料が入ると、困っている朝鮮の学生や老人に惜しげもなく分け与えてしまい、自分はいつも金欠だったという有名な話があります。職場では「浅川君の給料袋は、家に帰るまでに軽くなっている」と笑い話にされていたそうですが、そこには呆れよりも、彼の人徳に対する敬愛の念が含まれていました。仕事においてはプロフェッショナルであり、私生活では聖人のような無欲さを見せる。そんな巧の姿は、当時の官僚組織の中にあって、一服の清涼剤のような存在だったに違いありません。
植民地支配の矛盾と葛藤の中で貫いた共生の意志

三・一独立運動の衝撃と武力ではなく心で向き合う決意
1919年(大正8年)、朝鮮半島全土を揺るがす「三・一独立運動」が勃発しました。日本の統治に対する朝鮮民衆の積もり積もった不満が爆発し、独立を求める叫びが各地で上がったのです。この出来事は、総督府の役人であった浅川巧にも大きな衝撃を与えました。武力による鎮圧が行われ、多くの血が流れる状況に、巧は心を痛めました。彼は、自分自身が「支配する側」の組織に属しているという事実に、改めて苦悩したことでしょう。
しかし、巧はこの混乱の中で、日本人としての立場を放棄するわけでも、朝鮮の人々を敵視するわけでもありませんでした。彼は「力で押さえつけるのではなく、心で向き合うこと」こそが唯一の解決策であると信じました。兄や柳宗悦と共に、彼は文化を通じて相互理解を深める道を探り続けました。柳が日本の新聞に寄稿した『朝鮮人を想ふ』という文章は、当時の日本社会に大きな波紋を呼びましたが、巧もその精神を共有し、現場で実践しようとしました。
独立運動の直後、日本人の間では朝鮮人への恐怖や不信感が高まっていましたが、巧は変わらずパジ・チョゴリを着て、朝鮮の友人たちと会い続けました。周囲からは「危険だ」「朝鮮人の肩を持つのか」と白い目で見られることもあったはずです。それでも彼が態度を変えなかったのは、政治的な対立を超えたところに、人間同士の信頼関係があると確信していたからです。この時期の彼の行動は、静かではありますが、非常に勇気ある「抵抗」であり「平和への意思表示」でした。
柳兼子の歌声に込めた祈りとそれを支えた朝鮮の友人たち
この困難な時期に、巧たちの活動を支えたもう一人の重要人物が、柳宗悦の妻であり声楽家の柳兼子です。彼女は朝鮮を訪れ、各地で音楽会を開きました。兼子の圧倒的な歌声は、言葉や政治の壁を越えて、朝鮮の人々の心に深く響きました。巧は、この音楽会の開催に奔走し、会場の手配や宣伝に尽力しました。音楽会には多くの朝鮮人が詰めかけ、中には日本の官憲の監視下で行われたものもありましたが、会場は感動の涙で包まれたといいます。
特に印象的なのは、兼子の歌声に、会場を埋め尽くした朝鮮の人々が涙を流して聴き入ったという光景です。言葉も立場も異なる彼らが、一つの音楽を通じて心を通わせた瞬間でした。巧の友人である朝鮮の知識人たちも、兼子の歌声の中に、支配者としての傲慢さではなく、純粋な芸術への愛と、朝鮮民族への敬意を感じ取りました。巧はその光景を舞台袖で見守りながら、芸術が持つ「分断を修復する力」を改めて確信したに違いありません。
兼子のコンサートの成功は、巧や柳にとって大きな希望となりました。「政治では解決できないことも、芸術と心を通わせることで乗り越えられる」。この信念は、後の美術館設立や工芸研究の原動力となっていきました。巧は、友人たちが兼子を温かく迎え入れてくれたことに感謝し、その絆をさらに強固なものにするために、自らの役割を果たそうと心に誓ったのです。
支配する側の役人としてそれでも友であり続けようとした苦悩
しかし、浅川巧の心中には、常に消えない葛藤があったはずです。どんなに個人的に親しく付き合っても、公的には彼は「朝鮮総督府」の職員であり、朝鮮の人々から搾取するシステムの一部に組み込まれていました。林業試験場の仕事も、見方によっては「日本の利益のために朝鮮の資源を管理する」ものでした。巧はその矛盾を痛いほど理解していました。「私は彼らの真の友と言えるのか?」「私のやっていることは偽善ではないか?」という問いは、夜毎、彼の胸を去来したことでしょう。
ある時、巧は日記に自らの無力さを嘆く言葉を書き残しています。友人たちが不当に逮捕されたり、言論を弾圧されたりする中で、彼を救う力を持たない自分への苛立ち。それでも彼は、役人を辞める道を選びませんでした。辞めて日本に帰ることは簡単ですが、それは朝鮮を見捨てることと同義だと感じていたのかもしれません。「ここに留まり、自分ができる最大限のことをする」。それが、植林であり、工芸の保護であり、日々の誠実な交際でした。
彼は、自分が日本人であることを否定せず、かといって朝鮮人に成り代わることもできないという「境界の人」としての孤独を引き受けました。その苦悩があったからこそ、彼の言葉や行動には深みがあり、上辺だけの親善ではない、血の通った「共生」の姿勢が生まれたのです。彼が貫いたのは、国家という大きな主語ではなく、「私とあなた」という個人の関係を死守することでした。
浅川巧が残した緑の山と名著『朝鮮陶磁名考』の功績

木も人もその土地に合う方法で育てる画期的な養苗法の確立
内面的な葛藤を抱えながらも、浅川巧は仕事において驚くべき成果を上げていきます。その最大の功績の一つが、朝鮮五葉松(チョウセンゴヨウ)の「露天埋蔵法」の実用化です。当時、朝鮮の山林緑化のために様々な樹種の種子が蒔かれましたが、乾燥した気候と硬い種皮のせいで、発芽率は極めて低いものでした。巧は、自然界で種子がどのように冬を越し、春に芽吹くかを徹底的に観察しました。
そして彼は、採取した種子をすぐに蒔かず、あえて冬の間、屋外の土の中に埋めて寒さにさらす方法を考案しました。こうすることで種子は適度な湿り気を保ちつつ、冬の寒さを経験し、春になると一斉に発芽スイッチが入るのです。これは、朝鮮の厳しい冬を「敵」と見なすのではなく、発芽に必要な「プロセス」として利用する、まさに逆転の発想でした。「木も人も、その土地の風土に合った方法でなければ育たない」。この信念に基づいた養苗法により、発芽率は劇的に向上し、朝鮮全土の緑化事業に大きく貢献しました。
この技術は、単なるマニュアルの作成では終わりませんでした。巧は自ら現場を回り、現地の作業員たちに手取り足取り指導しました。彼の指導は、上からの押し付けではなく、朝鮮の自然への敬意に満ちたものでした。今日、韓国の山々が緑に覆われている背景には、巧が泥まみれになって確立した、この「命を育む技術」があったことを忘れてはなりません。
柳宗悦らと設立に奔走した朝鮮民族美術館という希望の砦
林業での成功と並行して、巧は兄や柳宗悦と共に、朝鮮の文化遺産を守るための巨大なプロジェクトに着手します。それが「朝鮮民族美術館」の設立です。当時、近代化の波の中で、朝鮮固有の古美術や民具は「古臭いもの」「価値のないもの」として急速に失われつつありました。柳と浅川兄弟は、これらを収集し、保存し、展示することで、朝鮮の人々に自国の文化への誇りを取り戻してもらいたいと願いました。
美術館の設立は困難を極めました。資金集め、場所の確保、そして何より総督府からの冷ややかな視線。しかし巧たちは諦めませんでした。巧は実務担当として、収蔵品の管理や展示計画に奔走しました。そして1924年、景福宮の中に朝鮮民族美術館が開館します。そこには、高価な国宝級の美術品だけでなく、巧が集めた庶民の膳や、柳が愛した白磁の壺が並びました。
この美術館は、単なる観光施設ではありませんでした。植民地支配下において、朝鮮民族の精神的支柱を守る「希望の砦」でした。多くの朝鮮の人々がここを訪れ、自分たちの祖先が作り出した美しさに涙し、勇気づけられました。巧にとって、この美術館は、政治的な無力感に対する精一杯の回答であり、未来への種まきだったのです。
陶磁器の歴史と美を体系化した研究成果と浜田庄司らとの交流
浅川巧の研究者としての集大成が、著書『朝鮮陶磁名考』です。これは、朝鮮の陶磁器の名称や用途、歴史的背景を、文献と実地調査に基づいて詳細に考証した画期的な一冊です。それまで感覚的に語られることが多かった朝鮮陶磁の世界に、初めて学術的な光を当てたのです。彼が分類した名称の多くは、現在でも定説として使われており、その慧眼には驚かされます。
この研究の過程で、巧は浜田庄司、河井寛次郎、富本憲吉、さらにはバーナード・リーチといった、後に民芸運動を牽引する一流の芸術家たちとも深く交流しました。彼らは朝鮮を訪れると必ず巧を頼り、巧の案内で窯跡を巡りました。彼らは巧の知識の深さと、対象物を見る目の確かさに舌を巻き、彼を「同志」として尊敬しました。
特に浜田庄司は、巧の人間性に深く惹かれていました。巧が語る陶磁器の話は、単なる形や色の話にとどまらず、それを使った人々の暮らしや、作った職人の息遣いにまで及びました。巧にとって工芸研究とは、物を通じて「人間」を知ることであり、その姿勢は民芸運動の精神的支柱の一つとなりました。『朝鮮陶磁名考』は、彼が愛した朝鮮の土と火、そして人へのラブレターでもあったのです。
浅川巧の早すぎる死と忘憂里の丘に響いた嘆きの声

激務の果てに40歳で倒れた浅川巧の壮絶な最期
昭和6年(1931年)4月。林業試験場での激務に加え、工芸研究、執筆活動と、休む間もなく走り続けてきた浅川巧の体に限界が訪れました。植樹祭の準備などで無理を重ねた彼は風邪をこじらせ、それが急性肺炎へと悪化しました。当時の医療技術では肺炎は命に関わる病でした。高熱にうなされながらも、巧は最後まで仕事のこと、そして朝鮮の家族や友人のことを気にかけていたといいます。
4月2日、浅川巧は静かに息を引き取りました。享年40歳。あまりにも早く、あまりにも突然の死でした。彼がやり残したこと、これからやりたかったことは山ほどあったはずです。養苗の研究も道半ばであり、執筆中の原稿も机の上に残されていました。彼の死の知らせは、瞬く間に京城中に広まりました。日本人社会だけでなく、彼を知る多くの朝鮮の人々が、その早すぎる死を悼み、悲しみに暮れました。
こんな日本人は初めてだと涙しわれ先に棺を担いだ朝鮮の人々
浅川巧の葬儀の日、そこには信じられない光景が広がりました。巧の自宅の前には、別れを惜しむ人々で溢れかえっていました。その多くは、彼と交流のあった朝鮮の人々でした。そして出棺の時、誰からともなく声が上がりました。「私が担ぎたい」「いや、私が担ぐんだ」。朝鮮の伝統では、他人の、しかも異民族の棺を担ぐことは稀なことです。しかし、人々は争うようにして巧の棺を担ごうとしました。
「こんな日本人は初めてだ」「彼は私たちの本当の友だった」。口々にそう言いながら、人々は涙を流して葬列に加わりました。長い長い葬列は、悲しみに包まれた京城の街を進みました。それは、浅川巧という人間が、いかに深くこの土地の人々に愛されていたかを示す、何よりの証でした。宗教も、民族も、立場の違いも、彼の棺の前では無意味でした。そこにあったのは、一人の誠実な人間を失った純粋な悲しみだけでした。
彼の遺体は、本人の遺言もあり、日本には帰らず、ソウル郊外の忘憂里(マンウリ)にある共同墓地に埋葬されました。「朝鮮の土になりたい」。その願い通り、彼は愛した朝鮮の大地に抱かれて眠りにつきました。墓碑には、兄・伯教の筆による文字が刻まれ、その側面には、朝鮮の友人が贈った灯籠が据えられました。
浅川巧の遺志を継いだ兄の伯教と『朝鮮陶磁名考』出版
巧の死後、兄の浅川伯教は弟が病床でも気にかけ、未完となっていた原稿を整理し、一冊の本として出版しました。それが『朝鮮陶磁名考』です。巧が生前に出版した『朝鮮の膳』が木工品への愛を綴ったものであったのに対し、この遺作は彼が長年心血を注いだ陶磁器研究の集大成でした。兄の手によって世に出されたこの本は、朝鮮陶磁の名称や歴史を体系化した画期的な名著として、現在でも高く評価されています。
兄・伯教にとって、巧の死は身を引き裂かれるような痛みでした。弟を朝鮮に呼び寄せたのは自分であり、その弟が自分よりも先に逝ってしまったのですから。しかし伯教は、弟が愛した朝鮮に留まり続けました。巧が始めたことを途絶えさせてはいけないという思いが、兄を支えました。『朝鮮陶磁名考』は、兄弟の絆の証であり、巧が朝鮮の土と火の中に見た「美の発見」を後世に伝える貴重な遺産となりました。
浅川巧をもっと知るための本・資料ガイド
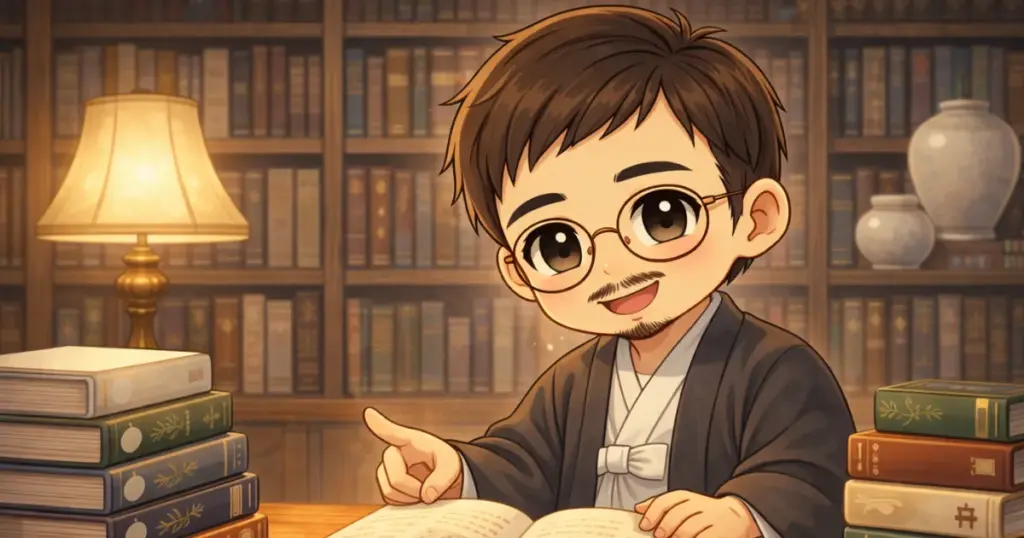
小説『白磁の人』が描く浅川巧の清冽な生き方
浅川巧の名を一般に広く知らしめたきっかけとなったのが、小説**『白磁の人』(江宮隆之 著 / 河出文庫 他)**です。著者の江宮隆之は、巧と同じ山梨県出身。同郷の先人が朝鮮で成し遂げた偉業に光を当てた本作は、史実をベースにしたフィクションですが、巧の清廉潔白な人柄と、李青林(モデルは実在の友人たち)との友情が感動的に描かれています。
特に、林業試験場での苦闘や、陶磁器への没頭ぶり、そして涙の葬列のシーンは、読者の胸を熱くします。「歴史の教科書には載らないけれど、こんな素晴らしい日本人がいた」という事実を知るための入り口として、最適な一冊です。映画化もされており、映像で巧の生き方に触れることもできます。
随筆『朝鮮の膳』から読み解く浅川巧の温かい視点
浅川巧自身の言葉に触れたいなら、『朝鮮の膳』(浅川巧 著 / 講談社学術文庫 他)は外せません。生前に出版された唯一の著書であるこの随筆集は、彼が愛した「膳(ソバン)」についての詳細な研究記録であり、同時に優れたエッセイでもあります。
学術的な分類や寸法の記録だけでなく、「なぜこの形なのか」「どうやって使われてきたのか」という考察の端々に、朝鮮の人々の暮らしへの敬意が滲み出ています。読んでいると、オンドルの部屋で家族が膳を囲む温かい風景が目に浮かんでくるようです。彼が「物」を通して「人」を見ていたことがよく分かる、体温を感じる名著です。文庫版などで併録されている『朝鮮陶磁名考』も必読です。
評伝『朝鮮の土となった日本人』が迫る史実
『朝鮮の土となった日本人 ——浅川巧の生涯』(高崎宗司 著 / 草風館 他)は、小説よりもさらに踏み込んで、史実としての浅川巧を知りたい方におすすめの本格的な評伝です。歴史学者の高崎宗司氏が綿密な取材と資料発掘を行い、巧の生涯を客観的かつ詳細に再構成しています。
特に、三・一独立運動前後の巧の動向や、彼を取り巻く人間関係、林業技術者としての具体的な業績について深く掘り下げられています。美談として語られがちなエピソードの背景にある歴史的事実や、当時の複雑な社会情勢も理解できるため、歴史好きや「ガチ勢」も納得の内容です。巧が単なる「いい人」ではなく、苦悩し、闘った「思想家」であり「実践者」であったことが浮き彫りになります。
朝鮮の土となった浅川巧が現代に伝える共生のメッセージ

植民地時代という困難な時代にあって、林業技手として「緑」を育て、工芸研究家として「白磁の美」を守り、そして何よりも一人の人間として朝鮮の人々と「心」を通わせた浅川巧。彼の40年という短い生涯は、まるで彼が愛した白磁のように、素朴でありながら、決して色あせない輝きを放っています。
彼は、国家や民族という大きな枠組みで人を判断することを拒み続けました。「どこの国の人か」ではなく、「目の前のその人とどう向き合うか」。彼が貫いたのは、その極めてシンプルで、しかし実行するには最も困難な「個としての愛」でした。彼が植えた木々は今も韓国の山々で緑を茂らせ、彼が見出した工芸の美しさは、現代のデザインにも大きな影響を与え続けています。しかし、彼が残した最大の遺産は、忘憂里の墓地に眠る彼自身が証明している、「人は理解し合える」という希望そのものではないでしょうか。
現代を生きる私たちもまた、様々な分断や対立の中にいます。しかし、浅川巧の生き方は、私たちに静かに問いかけています。「あなたは、隣人の言葉を話そうとしていますか?」「相手の文化を、心から美しいと思えますか?」と。国境を越えるとは、物理的に移動することだけではありません。相手の懐に飛び込み、共に笑い、共に泣くこと。浅川巧が遺した共生のメッセージは、100年の時を超えて、今こそ私たちの心に深く響くのです。









コメント