こんにちは!今回は、室町幕府の最盛期を築き、天皇家の権威さえもしのいだ「室町の絶対王者」、足利義満(あしかがよしみつ)です。
わずか11歳で将軍となり、半世紀続いた南北朝の動乱を終わらせ、明の皇帝から「日本国王」の称号を獲得。黄金の「金閣寺」を建て、能楽の世阿弥を見出し、美と権力を独占した彼の人生は、まさに栄華の極みといえます。
この男が目指したのは将軍か、それとも皇帝か。栄光と謎に満ちた51年の生涯をまとめます。
11歳で将軍となった足利義満と細川頼之の教育

祖父・尊氏の死から半年、待望の跡継ぎ「春王」の誕生
足利義満がこの世に生を受けたのは、1358年(延文3年)のことです。この年は、室町幕府の創始者である祖父・足利尊氏が亡くなった年でもありました。尊氏の死から百日あまり、入れ替わるようにして誕生した男の子は「春王(はるおう)」と名付けられました。
春王の幼少期は、決して穏やかなものではありませんでした。当時は北朝(幕府側)と南朝の戦いが激化しており、南朝軍が京都に攻め込んでくることも珍しくなかったのです。わずか4歳の時には、南朝軍の侵攻を避けて建仁寺に身を寄せ、その後、播磨国(現在の兵庫県)の守護大名・赤松氏の白旗城へと避難したこともありました。幼い心に刻まれた「逃げ惑う記憶」や「戦乱の恐怖」は、のちに彼が何よりも秩序と安定を求め、強力な権力によって乱世を終わらせようとする原動力になったのかもしれません。
父義詮の急死と「将軍指名」という劇的な運命の幕開け
京都に戻り、少しずつ将軍家の若君としての自覚が芽生え始めた矢先の1367年12月(貞治6年)、再び運命が大きく動きます。父である第2代将軍・足利義詮(よしあきら)が病に倒れ、危篤状態に陥ったのです。義詮は枕元に管領(かんれい)の細川頼之(ほそかわよりゆき)を呼び寄せ、後事を託しました。
『太平記』などの記録によれば、義詮は幼い春王を頼之に託し、「頼之を父と思わしめよ(頼之を本当の父だと思って従え)」と言い残したとされます。その時、春王はまだ満9歳。翌年、父が37歳の若さで世を去ると、春王は元服して「義満」と名乗り、1368年には数え年11歳で征夷大将軍に就任します。母である側室の紀良子(きの りょうし)が不安げに見守る中、幼き将軍の治世は、父の死という喪失と、大人たちの思惑が渦巻く中で幕を開けたのです。
幼き将軍を厳しく鍛え上げた「管領細川頼之」の手腕
父の遺言を受けた細川頼之は、義満にとって「第二の父」であり、同時に「鬼軍曹」のような存在となりました。四国の守護大名として実力を磨いてきた頼之は、幼い将軍をただのお飾りにはしませんでした。彼は1370年代(応安年間)に「応安大法」と呼ばれる土地制度の改革などを断行し、幕府の権威と財政基盤を強化する一方で、義満に対して徹底的な帝王学を叩き込みます。
頼之の教育は厳格そのものでした。彼は義満に、武芸だけでなく、漢詩や和歌、有職故実といった教養を身につけさせました。これには、粗野な武士集団と見られがちだった幕府を、朝廷や公家と対等に渡り合える組織にするという頼之の深謀遠慮があったのです。義満がのちに公家社会を自在に操る素地は、この時期の頼之の薫陶によって作られたといっても過言ではありません。義満にとって頼之は、頼れる背中であると同時に、常にその影を感じざるを得ない巨大な壁でもありました。
花の御所が完成し、京の支配者として自我を育む足利義満
頼之の補佐のもとで成長した義満は、やがて自らの権力を目に見える形で示し始めます。それが、京都の室町に造営した壮大な邸宅です。正式には「室町殿(むろまちどの)」と呼ばれたこの邸宅は、鴨川の水を引いた優美な庭園を持ち、四季折々の花々が植えられたことから、やがて「花の御所(はなのごしょ)」という名で呼ばれるようになったと伝わっています。
1378年(永和4年)前後、義満が20歳を迎える頃に移り住んだこの場所は、単なる住まいではありません。ここは幕府の政庁であり、同時に公家たちをも招き入れる外交の場でもありました。日々執り行われる華やかな儀式、出入りする高貴な人々。その中心に座る若き義満は、自分がもはや「頼之に守られた子供」ではなく、この京の都の新たな支配者であることを自覚し始めていたのでしょう。花の御所の完成は、義満の自我の目覚めと、これから始まる独裁的な権力行使の舞台装置が整ったことを意味していたのです。
「康暦の政変」で自立した足利義満と守護大名の壁

育ての親・細川頼之の失脚と義満に訪れた心理的自立の刻
花の御所での生活が始まって間もない1379年12月(康暦元年)、義満の人生を揺るがす大事件が起きます。「康暦の政変(こうりゃくのせいへん)」です。長年、幕政を牛耳ってきた細川頼之に対し、斯波氏や土岐氏といった他の有力守護大名たちが反発し、頼之の罷免を求めて御所を包囲したのです。クーデターとも言えるこの事態に、21歳の義満は究極の選択を迫られました。育ての親を守るか、それとも大名たちの要求を呑むか。
結果として、義満は頼之を罷免しました。育ての親であり、最高の政治家でもあった頼之は、幕政の中心から遠ざかることになったのです。この決断が義満の心にどれほどの葛藤をもたらしたかは想像に難くありません。しかし、父のように慕っていた頼之がいなくなったその瞬間から、義満は「誰にも頼れない」という冷徹な現実を突きつけられたのです。この喪失体験こそが、彼を甘えのある若者から、冷酷な計算も辞さない真の政治家へと変貌させるターニングポイントとなりました。
斯波義将の台頭と「花の御所」を中心とした新体制の構築
頼之失脚後、管領として幕政の中心に座ったのは、クーデターを主導した斯波義将(しばよしゆき)でした。義将は頼之とは対照的に、守護大名たちの利益を代表する立場にありましたが、義満はこの老練な政治家をうまく使いこなしていきます。頼之という重石が取れたことで、義満はかえって諸大名の上に君臨する「調停者」としての立場を強化していきました。
義満は、斯波義将ら有力者たちを花の御所に集め、幕府の意思決定機関を再編していきます。これまでは頼之の独壇場だった政治が、将軍と有力守護たちの合議、そして最終的には将軍の裁断によって決まるシステムへと移行していったのです。義満は、頼之が去った穴を嘆くのではなく、その空白を利用して、自分自身が名実ともに幕府の頂点に立つ体制を作り上げました。
美少年「世阿弥」との出会いが義満に植え付けた美と権威の感覚
政治的な自立を果たしていく一方で、義満は文化的な面でも大きな出会いを果たします。1378年、今熊野神社での能の興行において、当時15歳ほどの少年、観世丸(のちの世阿弥)を見初めたのです。当時、猿楽(能)はまだ身分の低い芸能とされていましたが、義満はこの少年の類まれな美貌と、並外れた才能に魅了され、自らの庇護のもとに置きました。
貴族社会では美少年を庇護することが一種のステータスとされていましたが、義満が世阿弥に示した関心は、単なる個人的な嗜好ではなく、その優れた芸能の才能への強い評価に基づいていたのです。義満は世阿弥を身近に置き、公然と彼を庇護しました。祇園祭や他の公的な場においても、将軍が認める芸能者として彼を扱うことで、「将軍が認めたものは、身分がいかに低くても価値がある」という義満の美意識と権威の宣言を示していたのです。世阿弥という原石を見出し、磨き上げる過程で、義満は「美」さえも自らの権力の一部として取り込む術を学んでいったのです。
悲願の「南北朝合一」を成し遂げた足利義満の剛腕

後円融天皇との確執を乗り越え、朝廷支配を盤石にするまで
政治と文化の両面で自信を深めた義満は、いよいよ聖域である「朝廷」へと手を伸ばします。当時の北朝の治天の君(事実上の君主)は、義満の従兄弟にあたる後円融上皇(ごえんゆうじょうこう)でした。1382年、後円融天皇は子の後小松天皇に譲位し、院政を開始していましたが、義満はこの新体制に深く介入しました。
義満は、まだ幼い後小松天皇を自らの保護下に置き、上皇を無視して公家たちを直接指揮し始めます。これに激怒した後円融上皇と義満の対立は深刻化し、1383年には上皇が持仏堂に立て籠もって切腹を宣言したり、妊娠中の妃を殴打したりする事件まで発生しました。しかし義満は動じません。むしろこの混乱を好機と捉え、「上皇のご乱心」を理由にその政治権限(治天の権)を奪い取り、自らが朝廷の事実上の管理者となってしまったのです。関白・二条良基(にじょうよしもと)から公家の作法を完璧に学んでいた義満にとって、もはや朝廷は「仰ぎ見る存在」ではなく、「管理すべき対象」となっていました。
有力守護を次々と挑発して潰した足利義満の謀略
朝廷を押さえた義満にとって、残る懸念材料は地方で強大な軍事力を持つ守護大名たちでした。義満は、一族内部の対立を煽り、相手が暴発したところを「幕府への反逆」として討伐するという冷徹な手法で、彼らを各個撃破していきます。
まず1390年(明徳元年)には美濃の土岐氏を「土岐康行の乱」で追い落とします。続いて翌1391年(明徳2年)には、西国11カ国の守護を兼ね、「六分の一殿」と呼ばれるほどの巨大勢力だった山名氏清・山名満幸らを挑発し、挙兵に追い込みました(明徳の乱)。義満は自ら総大将として出陣し、山名軍を壊滅させます。この一連の粛清により、幕府の軍事バランスは圧倒的に将軍直轄軍へと傾き、誰も義満に逆らえない独裁的な状況が作られました。
1392年、三種の神器が戻り義満の手で南北朝時代が終わる
国内の敵を一掃した義満が目指した最後のパズル、それが「南北朝の合一」でした。60年近くにわたり、日本に二人の天皇が存在するという異常事態は、幕府の権威にとっても大きな足かせとなっていました。義満は、南朝の後亀山天皇(ごかめやまてんのう)に対し、和平交渉を持ちかけます。
そして1392年(明徳3年)、ついに後亀山天皇が吉野の山を下り、三種の神器が北朝の後小松天皇のもとへ渡されました。この際、義満は南朝に対し、所領の安堵だけでなく、今後は北朝と南朝が交互に皇位を継承する「両統迭立(りょうとうたいりつ)」という約束を交わしていたとされます。神器が戻り、天皇が一人になった瞬間、義満は「動乱の時代を終わらせた英雄」としての地位を不動のものにしました。武力で敵をねじ伏せるだけでなく、高度な政治的駆け引きで歴史的な難題を解決したこの功績により、義満の権威は天皇さえも凌駕する領域へと突入していくのです。
「日本国王」として国際舞台へ登場した足利義満
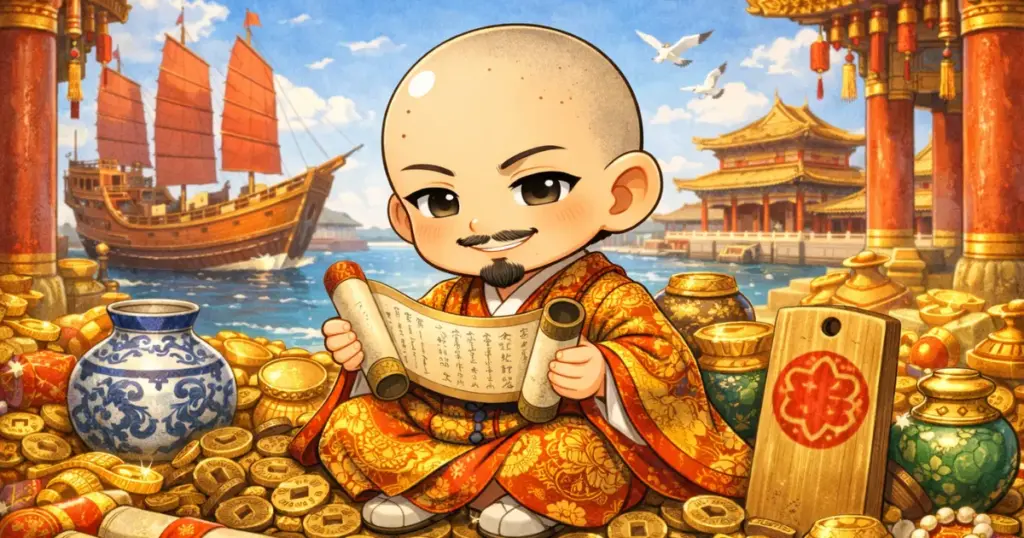
将軍職を息子に譲り、自由な「大御所」となって得た強権
南北朝合一を成し遂げた義満は、誰も予想しなかった驚きの一手を打ちます。1394年12月(応永元年12月)、義満は9歳の嫡男・足利義持(よしもち)に将軍職を譲り、翌1395年6月には自らも出家してしまったのです。
しかし、これは引退ではありません。むしろ、将軍という枠組み、朝廷の官位という制約から解き放たれ、より自由で強大な「大御所」として振る舞うための戦略でした。この時期からの義満の動きは、あまりに複雑かつスピーディーです。読者の皆さんのために、義満が「国王」へと変貌していく流れを整理してみましょう。
| 年 | 出来事 | 義満の狙いと状態 |
|---|---|---|
| 1394-95年 | 将軍職を義持に譲り出家 | 形式的な地位を捨て、実権のみを保持する「大御所」へ。 |
| 1399年 | 応永の乱(大内義弘を討伐) | 西国の最大勢力を排除し、貿易利権と軍事力を独占。 |
| 1401年 | 明へ使節を派遣 | 正式な国交樹立を目指し、独自の外交を開始。 |
| 1402年 | 明から「日本国王」に冊封される | 天皇とは別の、国際的な正統性を持つ君主となる。 |
| 1406-07年 | 妻・日野康子を准母(女院)に | 皇室と親族関係を擬制し、自らも皇族に準ずる立場へ。 |
このように、将軍職を譲ったあとの義満こそが、真に恐ろしい権力者だったのです。
西国の雄「大内義弘」の粛清と応永の乱による権力集中
出家してフリーハンドを得た義満が、真っ先に標的にしたのは、西国の有力大名・大内義弘(おおうちよしひろ)でした。大内氏は九州・中国地方に強大な勢力を持ち、朝鮮半島とも独自に貿易を行うなど、いわば「西の独立王国」のような存在でした。義満はこれを許しませんでした。
1399年、義満は大内義弘に対し、上洛を迫るなど執拗な圧力をかけ、ついに堺で挙兵させます(応永の乱)。義満は自ら大軍を率いてこれを鎮圧。大内義弘が討たれたことで、西国の貿易ルートや博多の支配権はすべて義満の手中に落ちました。これで国内に義満の命令に背ける勢力は皆無となり、彼は日本列島の真の支配者として、次なる「世界」への扉を開く準備を整えたのです。
明の永楽帝から「日本国王」に冊封され、勘合貿易の富を握る
応永の乱で西国の大名勢力を一掃した義満は、次なるターゲットを「世界」に向けました。当時の中国・明は、第2代皇帝・建文帝の時代でした。1401年、義満は「日本国王源道義(げんどうぎ)」という名義で国書を送ります。建文帝はこれを受け入れ、義満を「日本国王」として正式に冊封しました。
ところが翌1402年、明でクーデターが起き、建文帝は叔父の永楽帝(えいらくてい)によって皇位を奪われてしまいます(靖難の変)。義満の対応は素早いものでした。彼は新皇帝の永楽帝に対しても直ちに国書を送り、巧みに外交関係を維持したのです。永楽帝もこれを歓迎し、正式な通交を認めました。こうして義満は「日本国王」として明の朝貢体制に組み込まれ、1404年から本格的な勘合貿易(日明貿易)がスタートします。これにより、明の銅銭や高級織物が日本にもたらされ、幕府には莫大な利益が転がり込みました。この富こそが、義満の権力を支える最大のエンジンとなったのです。
日野康子を女院とし、皇室並みの儀礼を行った義満の真意
富と武力を極めた義満が最後に向かった先は、やはり皇室でした。彼は自らの正室・日野業子(ひのなりこ)の死後、日野資康の娘である日野康子(ひのやすこ)を継室に迎えていました。
1406年、後小松天皇の生母・通陽門院が亡くなると、義満は素早く動きます。彼は康子を、後小松天皇の「准母(じゅんぼ=母親代わり)」とし、翌1407年には「准三宮」の地位を与え、さらに「北山院」という院号を宣下され、女院の身分を獲得させたのです。 これは前代未聞の事態でした。臣下の妻が、天皇の母親扱いとなるのです。これにより、康子の夫である義満自身も、天皇の「准父」、つまり「お父さん」のような立場を手に入れました。義満は、天皇に拝謁する際も臣下の礼をとらず、対等、あるいはそれ以上の態度で接するようになります。彼は制度の枠組みを内側から食い破り、天皇家という血統の壁さえも、儀礼というマジックを使って乗り越えようとしていたのです。
黄金の「金閣寺」を築いた足利義満の美意識と偏愛

現世に極楽浄土をつくる、権力の視覚化としての「北山第」
絶頂期を迎えた義満は、1397年(応永4年)から京都の北山に壮大な別荘の造営を始めます。翌1398年(応永5年)に、その象徴となる金閣(舎利殿)が完成しました。これが現在の鹿苑寺(ろくおんじ)、通称「金閣寺」を含む北山第(きたやまだい)です。
金閣の三層構造を見てください。ここには義満のメッセージが込められています。一層は「法水院(ほうすいいん)」と呼ばれる公家風の寝殿造(当初は白木素木)、二層は「潮音洞(ちょうおんどう)」と呼ばれる武家風の和様建築、そして三層は「究竟頂(くっきょうちょう)」と呼ばれる禅宗様の仏堂です。これらが一つに融合し、その頂点には王権の象徴である鳳凰が輝いています。これは「公家も武家も仏教勢力も、すべて私が統べる」という、義満の権力の宣言に他なりません。義満は、自分が住む場所を「聖地」と化すことで、自らを「現世の仏」あるいは「聖なる王」として演出しようとしたのです。
長男・義持を疎んじ、愛息・義嗣を溺愛した父としての矛盾
政治においては完璧なマキャベリストだった義満ですが、家庭人としては大きな矛盾を抱えていました。彼は、将軍職を譲った長男の義持を極端に冷遇し、逆に側室・藤原慶子の子である足利義嗣(よしつぐ)を溺愛したのです。
義嗣は容姿端麗で才能に溢れ、義満のお気に入りでした。義満は義嗣を皇族のように扱い、やがて後小松天皇の前で「若宮」(皇族に準ずる身分)として立たせようとしていました。一方、慎重な性格と評された義持は、父から期待されず、恐怖と屈辱の日々を送ります。この歪んだ親子関係は、義満という絶対権力者が抱える「孤独」の裏返しだったのかもしれません。
しかし義満の死後、この偏愛が義持による「父の全否定」という復讐の引き金となります。義持は重鎮・斯波義将の死後(1410年)、明との国交を断絶し、父の栄光だった勘合貿易も停止させてしまいました。そして1418年1月、義嗣自身も義持の密命を受けた富樫満成に殺害されるという悲劇的な結末を迎えたのです。
公家と武家の文化を融合させ、自らを演出した「北山文化」
義満の時代に花開いた「北山文化」は、伝統的な公家文化と、新興の武家文化、そして大陸からの禅文化が融合した、華やかで力強い文化でした。義満は能の世阿弥だけでなく、多くの芸術家や禅僧をパトロンとして支援しました。
しかし、これも単なる趣味ではありませんでした。義満は、和歌や蹴鞠(けまり)といった公家の独占物だった教養を武士も身につけるべきだと考え、自らがその手本となりました。彼が主催するサロンでは、公家も武士も僧侶も入り混じり、義満を中心に新たな価値観が生み出されていきました。「文化の力で朝廷を圧倒する」。それもまた、義満が目指した王権確立の一つの手段だったのです。
皇位簒奪の噂と足利義満の急死に残る謎

相国寺に入り、太上法皇のような最高権威となった晩年
最晩年の1407年(応永14年)頃、自らが創建した相国寺(しょうこくじ)が旧観に復興されました。義満は北山第を中心に活動しながら、この寺とも深い関わりを持つようになっていきました。公家たちの日記には、義満が法皇(出家した上皇)と同じような儀礼で動いていたことが記されています。
彼は政治の実権(将軍の力)、経済の支配権(日明貿易)、宗教的権威(禅宗の統率者)、そして皇室に準ずる身分(准父・院号)のすべてを手にしていました。あと彼に足りないものは「天皇」という称号そのものだけ。当時の人々、特に貴族たちは「義満はいずれ自分の子(愛する義嗣)を天皇にし、自らは皇帝として君臨するつもりではないか」と本気で恐れていました。これを「皇位簒奪(こういさんだつ)計画」と呼ぶ歴史家もいますが、この説については異説も多く、義満が本気で皇帝化を目指していたかどうかについては今も議論が分かれています。
1408年の突然死は暗殺か病死か?医学的見地と当時の記録
しかし、その野望(あるいは構想)は唐突に断ち切られます。1408年(応永15年)4月25日、義満は内裏で息子・義嗣の元服式を執り行いました。ところがその2日後の4月27日、義満は突然病に倒れます。一時は回復の兆しを見せたものの、5月4日に危篤となり、5月6日の午後6時前後に51歳の生涯を閉じたのです。
このあまりにタイミングの良い死は、当時から様々な憶測を呼びました。「明の使いから贈られた毒薬を盛られた」「朝廷による呪詛だ」「いや、疎まれていた長男・義持の陰謀だ」。現代の医学的見地からは、急性肺炎やインフルエンザ、あるいは毒殺説まで諸説ありますが、真相は闇の中です。具体的な病名は記録に残っていません。『応永記』などの同時代の記録に残るのは、ただ「病によりて薨(こう)ぜり」という簡素な記述のみです。絶対権力者のあっけない最期は、彼の人生そのものが巨大な謎であったことを象徴しているかのようです。
父の政策を全否定し「義満の痕跡」を消し去った4代将軍義持
義満の死後、4代将軍として実権を握ったのは、長年父に抑圧されてきた足利義持でした。義持の行動は迅速かつ徹底的でした。彼は父の葬儀が終わるやいなや、北山第(金閣を除く)を破却し、明との勘合貿易を「日本は神国であり、異国に頭を下げるべきではない」として一方的に中断させました。
さらに朝廷は義満の死後、すぐさま「太上法皇」の称号を贈ろうとし、また「恭献」という諡号(しご)も送られました。しかし義持と管領・斯波義将は、これらの尊号を辞退させてしまったのです。義持は、父が愛した弟・義嗣ものちに捕らえて殺害しています。父が築き上げた政策、外交、そして愛した者たち。義持によるこれら全ての「否定と消去」は、父・義満がいかに規格外の存在であり、その路線が当時の日本の常識といかにかけ離れていたかを逆説的に証明することになりました。
足利義満の野望と実像を知るための本・作品ガイド

皇位簒奪の真実に迫る衝撃の論考『室町の王権』
「足利義満は、天皇になろうとしたのではないか?」――この歴史学界を揺るがすスリリングな問いに挑むなら、今谷明氏の『室町の王権 足利義満の王権簒奪計画』(中公新書、1990年)が必読です。 本書では、義満がどのように朝廷の儀礼を緻密に模倣し、いかにして「王権」そのものを内側から乗っ取ろうとしたかが、まるで政治サスペンスのように描かれています。単なる野心家というだけでなく、伝統と権威を冷徹にハックしていく義満の知的な恐ろしさを味わえる、歴史ミステリーとしても一級の論考です。
“怪物”になる前の若き日の苦悩と成長『私本太平記』
完成された権力者ではなく、人間味あふれる義満に出会いたいなら、国民的作家・吉川英治氏の『私本太平記』(毎日新聞連載 1958-1959年、他)がおすすめです。 足利尊氏を主役とした長編ですが、物語の終盤、父・義詮の死を乗り越えようともがく若き日の義満が登場します。ここには、後年の冷酷な独裁者の影はまだ薄く、細川頼之の厳しい指導を受けながら、混乱する時代をどう収めるか悩み、成長していく等身大の青年の姿があります。「英雄の青春期」を知ることで、史実の義満像により深みが増すはずです。
芸能と権力の危うい共犯関係を描く『平家物語 犬王の巻』
義満が持っていた「美への執着」と「底知れぬ不気味さ」を体感するなら、古川日出男氏の『平家物語 犬王の巻』(河出文庫、2017年)が最適です。アニメ映画『犬王』の原作としても知られる本作では、能楽師たちのパトロンとして、彼らを支配し、利用し尽くす「プロデューサー」としての義満が描かれています。 彼はただの文化保護者ではありません。芸能の力を利用して民衆を熱狂させ、自身の権威付けに利用するしたたかな政治家です。現代的なロックやポップスのリズムを感じさせる文体の中で、義満のカリスマ性が異様に際立つ、刺激的な一冊です。
義満が封印した“熱き時代”への鎮魂歌『破軍の星』
義満が終わらせた「南北朝時代」がいかに熱く、切ない時代だったのかを知るには、北方謙三氏のハードボイルド歴史小説『破軍の星』(集英社、1988年刊行)を手にとってみてください。 主人公は南朝の貴公子・北畠顕家ですが、彼らが命を燃やして戦った混沌の時代を知ることで、それを力でねじ伏せ、管理された平和を作り上げた義満の凄み(あるいは冷徹さ)が逆説的に浮き彫りになります。「無秩序な情熱」と「管理された秩序」。義満が何を封印したのかを理解するための、最高の参考書となるでしょう。
天皇に迫った「室町の絶対王者」足利義満の軌跡

「この男は、皇帝か、それとも将軍か?」
足利義満の51年の人生を貫く根本的な問いがこれです。11歳で父を失い、動乱の世に放り出された少年は、一生を通じて「俺は何者か」という問いへの答えを探し続けました。武家のトップである将軍、朝廷のトップに準ずる准父、そして中華皇帝に認められた日本国王。彼はあらゆる権威をその身にまとい、日本史上、誰よりも高く、誰よりも強くあろうとしました。
彼が果たした役割は計り知れません。半世紀続いた南北朝の内乱を終わらせ、国内に平和をもたらしました。明との国交を開き、日本を東アジアの経済圏に組み込みました。そして、金閣寺に代表される北山文化を育み、今の私たちが「日本的」と感じる美意識の源流を作りました。彼は間違いなく、室町幕府を最強の政権へと押し上げた巨人でした。
しかし、その栄華は彼の死とともに、息子によってあっさりと否定されました。義満の野望は、今も金閣寺の黄金に映っていますが、それを継ぐ者はいなかったのです。完璧な権力者も、死ねばその意思までは残せない。義満の生涯は、権力の頂点を極めた男の栄光と、その後に訪れる儚さを、私たちに静かに語りかけています。









コメント