こんにちは!今回は、平安時代中期に生き、現代の私たちと同じように「物語」に心を焦がした文学好きの女性、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)を紹介します。
彼女は、京から遠く離れた田舎で『源氏物語』に憧れ、夢と現実のギャップに悩み、晩年には静かな信仰の中に救いを見出した人物です。その人生は、まさに「推し活」に熱中し、やがて大人になる過程で現実と折り合いをつけていく、等身大の人間ドラマといえます。
千年前に「物語」に救われ、そして翻弄された彼女の生き方は、今の私たちに何を語りかけてくれるのでしょうか。
菅原孝標女の原点となる上総国での物語への渇望

天神様の子孫である菅原孝標女の家系と父の愛
菅原孝標女は、寛弘5年(1008年)頃に生まれました。その名の通り、彼女は菅原孝標(すがわらのたかすえ)の娘です。菅原氏といえば、「学問の神様」として知られる菅原道真公を祖先に持つ名門の家柄であり、学問や文筆に優れた人物を多く輩出してきました。
父の孝標は受領(ずりょう)として地方官を歴任した人物ですが、同時に娘の「物語好き」という性格を深く理解し、愛した優しい父親でした。また、彼女の母は藤原倫寧の娘とされますが、幼少期には何らかの事情で離れて暮らしていた時期があったようです。さらに、僧侶となった異母兄・基円や、実務面で家を支えた同母兄・定義など、彼女を取り巻く家族は、彼女の感受性を育む揺りかごのような存在でした。
継母が語る源氏物語の世界に魅せられた幼少期
父の任国である上総国(現在の千葉県中部)で育った彼女にとって、文化の中心地である「京」は遥か彼方の夢の都でした。そんな田舎暮らしの彼女に、京の雅な空気を吹き込んだのが、継母である高階成行の娘(通称・上総大輔)です。
継母は教養豊かで、当時京で流行していた物語の話を幼い孝標女に語って聞かせました。特に、世に出たばかりの『源氏物語』の話は、少女の心に強烈な光を灯しました。「世の中には、光源氏というこの上なく美しい人がいるらしい」。継母の語る断片的なストーリーは、彼女の想像力を刺激し、まだ見ぬ世界への渇望を決定的なものにしたのです。ここで培われた想像力が、後の彼女の人生を貫く軸となります。
等身大の薬師仏を作って京への上洛を祈った日々
物語への憧れは、やがて信仰に近い祈りへと変わっていきます。彼女は自分と同じ背丈の薬師仏(薬師如来像)を造らせて、来る日も来る日も祈り続けました。
しかし、その祈りの内容は「家族の健康」や「家の繁栄」といった一般的なものではありません。「早く京へ帰して、物語をたくさん読ませてください」という、あまりにも純粋で世俗的な願いでした。このエピソードは、彼女の並外れた執着心を示すと同時に、幼い頃から「祈り」という行為が彼女の精神の安定装置であったことを示唆しています。皮肉にも、この時に捧げた一途な祈りの姿勢が、晩年の彼女を支える阿弥陀信仰の萌芽となっていたといえるでしょう。
菅原孝標女が旅した東海道の絶景と現実の厳しさ

伝説の旅立ちとなる上総国から京への長い帰路
彼女が数え年で13歳になる寛仁4年(1020年)、ついに父の任期が終わり、念願の帰京が決まります。上総国から京までの道のりは、数ヶ月にも及ぶ長い旅でした。この旅の記録は『更級日記』の冒頭を飾るハイライトであり、中世の紀行文としても極めて高い価値を持っています。
旅立ちの日、慣れ親しんだ家が解体される様子を見て、彼女は感傷に浸ります。昨日までの日常が消え、未知の世界へと踏み出す瞬間。それは「物語の世界」へ近づく喜びであると同時に、守られた子供時代との決別でもありました。
富士山や各地の風景を切り取った鋭い観察眼
旅の途中で彼女が目にしたのは、東国の雄大な自然でした。 特に富士山の描写は独特です。多くの人が「白く美しい山」と称える中で、彼女は日記に「山の色は深く青黒く、頂上は平らに削ぎ落とされたようだ」と記しています。
これは噴火活動が続いていた当時の富士山のリアルな姿(山肌の岩石や平らな火口付近)を捉えたものと言われています。既存の和歌のイメージに流されず、見たままを言葉にする彼女の観察眼と文才が、早くもここで発揮されています。また、武蔵国と相模国の境にある川を渡る際の心細さや、各地で聞いた悲恋の伝説など、彼女は風景の中に「物語」を見出しながら旅を続けました。
足柄山での鏡の盗難事件が予感させた将来の陰り
しかし、旅は美しいだけではありませんでした。難所である足柄山の麓に宿をとった際、彼女にとって衝撃的な事件が起きます。大切にしていた鏡が、何者かに盗まれてしまったのです。
当時、鏡は女性の身だしなみに欠かせない貴重品であり、それを旅の途中で失うことは大変な不吉さを意味しました。彼女はその悔しさと悲しみに涙を流したと記しています。美しく輝く物語の世界に向かっているはずが、現実は容赦なく大切なものを奪っていく。「物語」と「現実」の境界線が揺らぎ、残酷な現実が顔を覗かせた瞬間でした。この事件は、彼女がこれから歩むことになる「夢と現実の相克」を象徴する最初のつまずきだったのかもしれません。
菅原孝標女が源氏物語五十四帖を手に入れた至福の時

憧れの京で直面した継母との別れと孤独な環境
苦難の旅を終えて京に辿り着いた彼女を待っていたのは、大人の事情による切ない別れでした。文学の師であり、上総国での心の支えであった継母(上総大輔)が、父・孝標と別れることになり、家を去ってしまったのです。
「近いうちに必ず呼び寄せますからね」と言い残して去った継母でしたが、その言葉が実現することはありませんでした。その後、彼女たちが再び親密に交流する機会はほとんど訪れなかったようです。 また、実母や周囲の大人たちは、昼夜を問わず物語に没頭する彼女の健康や将来を案じていましたが、彼女の孤独を埋める術は物語以外にはありませんでした。京の現実は疫病の流行や不安定な治安など厳しく、彼女は閉じた部屋の中で孤独感を募らせていきました。
叔母から贈られた源氏物語全巻と部屋に籠もる昼夜
そんなある日、彼女の運命を変える贈り物が届きます。『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱母とも血縁関係にあるとされる叔母が、彼女のために『源氏物語』五十余巻をはじめとする、大量の物語本を贈ってくれたのです。
ついに手に入れた「源氏のすべて」。彼女の喜びようは尋常ではありません。「后(きさき)の位も何も欲しくない」と言い切るほど、彼女は物語の世界に没入しました。昼も夜も部屋に籠もり、御簾(みす)の中でひたすらページをめくる日々。読みたかった場面を誰にも邪魔されず、最初から最後まで通して読む快感は、現実の寂しさを完全に忘れさせてくれる至福の時間でした。彼女にとって物語は、単なる娯楽ではなく、生きるための酸素そのものだったのです。
物語に耽溺する娘を見守った父孝標の親心
一方で、そんな娘を見守る父・孝標の心境は複雑でした。普通なら「早く琴や習字を稽古しなさい」と叱るところですが、孝標は「物語を読んでいる時が一番幸せそうだ」と、娘の没頭を許容しました。
父もまた、受領として地方を回り、泥臭い実務と世間の荒波に揉まれてきた人物です。自分の力だけでは娘を高い地位につけてやれないという無力感や、現実社会の厳しさを知っていたからこそ、せめて娘が夢見ている間は、その「聖域」を守ってやりたいと思ったのかもしれません。 時折、父は「お前が宮仕えなどして出世したらいいのに」と口にしましたが、彼女はその言葉を「物語のような高貴な姫君になれるかもしれない」という方向で受け取ってしまいます。父の現実的な親心と、娘の空想的な解釈。このすれ違いもまた、不器用な親子の愛情の形といえるでしょう。
菅原孝標女が直面した肉親の死と物語からの覚醒

愛猫の死と姉との別れが突きつけた無常観
夢のような日々は長くは続きませんでした。ある時、彼女は迷い込んできた猫を「亡くなった大納言の姫君の生まれ変わり」だと信じ込んで可愛がりますが、その猫は屋敷の火事に巻き込まれ、焼死してしまいます。
さらに決定的だったのは、物語を共に楽しんだ仲の良い姉が、万寿元年(1024年)に出産のため実家に戻り、そのまま若くして亡くなったことでした。 信心深かった姉は死の間際、「私は少しも功徳を積まずに死んでしまうのが心残りだ」と嘆きました。大切にしていた猫の惨たらしい死と、最愛の姉との永遠の別れ。これらは彼女に対し、「物語のような奇跡は起こらない」「人は必ず死ぬ」という残酷な事実を突きつけました。
物語の姫君を夢見て婚期を逃した二十代後半の葛藤
姉の死後も、彼女は心の穴を埋めるように物語に縋りましたが、現実はシビアでした。当時、彼女は二十代後半から三十代へと年を重ねていきました。この時期は、当時の感覚ではもはや「若い娘」ではありません。周囲の女性たちが堅実に結婚し、家庭を築いていく中で、彼女だけが『源氏物語』の薄幸のヒロインである「夕顔」や「浮舟」のような、儚くもドラマチックな運命を待ち続けていました。
しかし、現実にそのような貴公子が現れるはずもありません。理想のロマンスと、現実の自分が置かれた状況のギャップ。彼女は徐々に、自分の生き方が世間からズレていることに気づき始め、焦燥感を募らせていきます。
夢のお告げを無視して物語を選んだ若き日の代償
この頃、彼女は何度か不思議な夢を見ています。ある時は僧侶が現れて、具体的に「法華経の第五巻を早く習いなさい」と告げました。これは深層心理からの警告――「虚構の世界(物語)」から離れ、「真実の世界(仏教)」へ向かえというメッセージでした。
しかし、若き日の彼女はこの警告を無視してしまいます。「まだ若いのだから、仏道修行は年を取ってからでいい。今は物語を読みたい」。そう先送りにしてしまったのです。 後年、彼女はこの時の判断を深く悔やむようになります。神聖な呼びかけよりも、世俗的な執着を選んでしまった自分への自責の念が、『更級日記』全体に静かな影を落としています。
菅原孝標女の宮仕えと平凡な結婚生活への着地
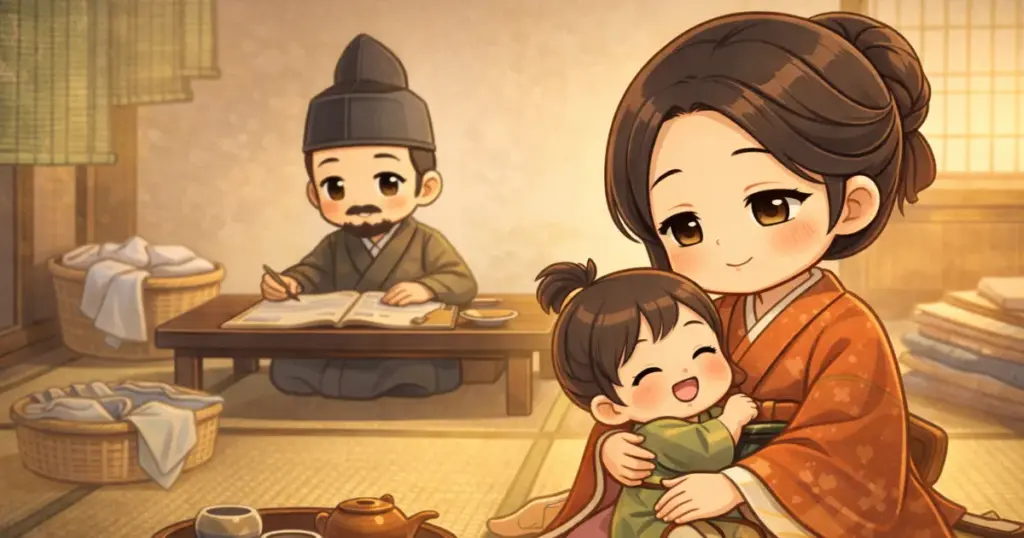
祐子内親王への出仕で見えた宮中の華やかさと限界
三十代に入り、彼女についに転機が訪れます。後朱雀天皇の皇女であり、母は藤原道長の娘(嬉子)という高貴な身分の祐子内親王(ゆうしないしんのう)への出仕が決まったのです。
憧れの宮中生活。内親王のサロンは明るく華やかで、彼女はそこで自身の教養を活かすことができました。 しかし、彼女の性格は内気で、きらびやかな宮廷の人間関係には完全には馴染めなかったようです。『更級日記』には、出仕しても実家に下がっていることが多かった様子が記されています。高齢の両親を案じる気持ちもあり、結局、彼女のキャリアは物語の女房たちのように長く続くことはありませんでした。そこで彼女が感じたのは、「自分はここの主役にはなれない」という、静かな疎外感だったのかもしれません。
源資通との歌のやり取りに残る淡い恋の記憶
宮仕えの中で、彼女の心にさざ波を立てた男性がいました。右中弁などを務めた実在の貴公子・源資通(みなもとのすけみち)です。 彼とは春の夜に御簾越しに語り合ったり、七夕の夜に「星の逢瀬」にちなんだ風流な和歌を贈り合ったりと、まるで物語のワンシーンのような交流がありました。
「もしかして、これが運命の恋?」と期待したかもしれません。しかし、資通との関係はそれ以上に発展することなく、淡い思い出として終わりました。彼は光源氏のように強引に彼女を連れ去ることはなく、あくまで「高貴な廷臣」と「出仕した女性」という一線を越えることはありませんでした。このエピソードは、現実の恋愛が決して物語のようには進まないことを、静かに、しかし残酷に示しています。
光る君ではない実務家・橘俊通との堅実な暮らし
宮仕えから遠ざかった後、彼女は橘俊通(たちばなのとしみち)と結婚します。俊通は、彼女が夢見ていたような「琴を弾き、和歌を詠む貴公子」ではなく、下野守(しもつけのかみ)や信濃守として地方を飛び回る、現実的な受領(ずりょう)階級の実務官僚でした。
ロマンスはありませんでしたが、俊通は経済力があり、家族を大切にする夫でした。彼女は夫の任国へは行かず、京で家を守る形をとりましたが、息子の仲俊をはじめとする子供にも恵まれ、「受領の妻」としての平凡ながら安定した幸せを受け入れます。 それは『源氏物語』のような夢の世界とは違いましたが、地に足のついた、温かい家庭生活でした。この結婚生活こそが、長年夢と現実の間で揺れ動いてきた彼女が辿り着いた、ひとつの「答え」だったのです。
菅原孝標女の晩年と静かなる祈りの日々

夫の任国へ同行せず京で留守を守った母としての強さ
結婚後、夫の俊通は信濃などの任国へ赴任しましたが、彼女は京に留まり、家の留守を預かることが多くなりました。かつて「どこか遠くへ連れ去ってほしい」と願った夢見がちな少女は、今や子供たちの将来を考え、現実的な判断で家を守る、たくましい母親となっていました。
夫との別居生活は寂しいものでしたが、たまに帰京する夫を迎え、家族で過ごす時間は穏やかなものでした。彼女はこの平穏が長く続くことを願っていましたが、運命は過酷でした。
夫俊通の死後に訪れた深い孤独と仏教への急傾斜
康平元年(1058年)、信濃での任期を終えて夫が帰京します。ようやく夫婦水入らずの老後が送れると思った矢先の同年秋、夫は病に倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまいました。 夫の死は、彼女にとって決定的な打撃でした。「物語の世界」への逃避も、「現実の家庭」という基盤も、すべて失われてしまったのです。
深い孤独の中で、彼女を救ったのは阿弥陀信仰でした。日記の終盤、彼女の夢に阿弥陀如来が現れ、手を差し伸べる場面が描かれます。彼女は亡き夫の供養と共に、自らの来世の救済を願い、ひたすら祈りを捧げるようになりました。それは単なる絶望からの逃避ではなく、すべての執着を手放し、静かに死と向き合うための精神的な到達点でした。
過去の自分を振り返り更級日記を綴った心の救済
夫の死からしばらく経った康平2年(1059年)以降、五十代となった彼女は、これまでの人生を振り返り、『更級日記』を書き上げたとされています。 物語に熱狂した少女時代、現実に打ちのめされた結婚生活、そして夫との死別。そのすべてを文章として書き残す際、彼女の胸にあったのはどんな思いだったでしょうか。
日記の終盤で、彼女は甥の菅原在良(すがわらのありよし)と月を見ながら歌を交わし、寂しさを慰め合っています。 「私の人生は物語のように華やかではなかったけれど、こうして生き抜いてきた」。 自らの人生を一つの作品として完結させること。それこそが、夢と現実の間で揺れ続けた彼女が最後に見つけた、魂の救済だったのかもしれません。
菅原孝標女をもっと知るための本・資料ガイド

ビギナーからマニアまで楽しめる奇跡の自叙伝『更級日記』
まずは何と言ってもご本人の著作です。「日記」というタイトルですが、今日起きたことを毎日記したものではなく、晩年になってから人生の節目を回想して綴った「自叙伝(回想録)」のスタイルをとっています。
原文で味わいたい方には、注釈が充実している『岩波文庫版』が王道ですが、古典が苦手な方には、人気作家・角田光代氏による現代語訳(河出書房新社など)や、『マンガ日本の古典』シリーズなどの漫画版から入るのがおすすめです。 その内容は、現代の推し活にも通じる「物語への熱狂的な愛」と、その後の現実との折り合い、そして老後の不安までを赤裸々に描いており、千年の時を超えて「これ、私のことだ」と共感できるポイントが満載です。
作者不詳だが孝標女の作とも囁かれる悲恋の物語『夜の寝覚』
平安後期の作り物語です。実はこの作品、正確な作者は分かっておらず、学術的には「作者不詳」とされています。 しかし、かつて「『更級日記』の作者である孝標女が書いたのではないか?」という説が提唱されたことがありました。物語の内容が、彼女が好んだ悲劇的な展開や、人間の内面を深く掘り下げる心理描写に富んでいるためです。 「物語に憧れ続けた彼女が、最後に読み手から書き手へ回ったのかもしれない」。学術的な定説ではありませんが、そう想像しながらこの悲恋の物語を読むと、また違った味わい深さが見えてくるでしょう。
田辺聖子が描く平安女性のリアルな心情『むかし・あけぼの』
『更級日記』を題材にした小説や解説書は多くありますが、特におすすめなのが田辺聖子氏の小説『むかし・あけぼの』です。 田辺氏は、孝標女を「何者かになりたくて、なれなかった女性」として温かく、かつ鋭く描いています。原文では淡々と書かれている夫との関係や、宮仕えでの挫折感などが、現代人にも通じる「生活の悩み」として鮮やかに蘇ります。 「古典のヒロインも、私たちと同じように悩んで生きていたんだ」と実感したい方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
夢と現実の間で揺れた菅原孝標女が現代に送る静かなエール

菅原孝標女の生涯は、一見すると「何も成し遂げなかった人生」に見えるかもしれません。政治を動かしたわけでも、歴史を変える大事件に関わったわけでもありません。
しかし、彼女が遺した「物語への愛」と「現実との葛藤」の記録は、現代を生きる私たちに深く刺さります。私たちもまた、小説や漫画、映画やSNSといった「物語」に夢中になり、時に現実の厳しさに打ちのめされながら生きています。彼女の姿は、そんな私たちの先駆者であり、同志です。
「現実がどんなに辛くても、物語を持つ人は強い」。そして「物語から覚めたあとの現実も、また愛すべき人生である」。彼女の生涯は、そんな静かなエールを、千年の時を超えて私たちに送り続けているのです。



コメント